地元の自然が生んだ素材を使い、地元の職人が受け継いできた技を用い、その土地の気候風土の中で暮らす人のための住まいとはどうあるべきかを模索し続ける由利設計工房の由利収氏。いかにも手間のかかるその手法にたどり着いたのは、技術の進歩による効率化で北から南まで画一的な住居が立ち並ぶ日本の家造りを見ていて感じた、ある違和感が出発点だった。やがてその理念に共感するクライアントが由利氏の元を訪れるようになる。
由利設計工房(中編) 社会に残る、100年持つ建築物を

その土地の素材を建築に生かすことで地域の自然環境の維持につながり、その建物がさまざまな形で利用され続けることで地域に社会的なストックが増え、そこで暮らす住民たちに地元の自然への愛着、さらには職人への敬意が生まれる。建築を通して、そんな循環をも生み出そうとしている由利氏が掲げるのは「100年残る建築物」。夢や理想ではなく、それを実現するために造られた100年後のストックが一つ、また一つ仙台に増えている。
社会に残る、100年持つ建築物を
—その土地の素材で造る、ということについてもう少しお聞かせください。
由利 日本の木はいま使われなくなっていて、自給率が2割ちょっとなんです。日本の国土の6割7割が森林なのに、おかしな話ですよね。僕らが使っている樹齢60〜70年の杉の木が立った状態で、柱一本分として値段を付けるとしたらどれぐらいだと思いますか。
—想像がつきません。
由利 それが、スーパーで売っている大根ぐらいなんですよ。100円ちょっとぐらいしかならない。立っている状態だとものすごい安いんですね。なので林業家はやっていけないんです。それを運び出して製材所で切って、乾燥して製材になるんですけど、そのときにようやく1本2,000円〜3,000円になるんです。それでもその程度です。

単価でいうと、製材しても輸入木材と同じくらいなんです。でも海外の木は、例えばカナダとか、畑みたいなところに大量に生えているものを機械で一気に切って、CO2を大量に排出しながらタンカーなどで運んでくる。だから日本の小さい町でも海外から来た木で家が建てられるんですが、同等の値段なら裏山の木を使った方が自然じゃないかと僕は思うんです。年間何百棟と大量に建てたいがために効率を求めて環境負荷をかけるのは、どうなんだろうと。環境的な問題だけではありませんが、僕は極力近場の木を使って地元の職人さんにやってもらう方が自然だろうと思ってやっています。
いま、泉に認定こども園(仙台みどり学園幼保連携型認定こども園やかまし村)を建てているのですが、国の予算取りから始まって、7月ぐらいに予算が決まって一般競争入札があって、来年度の4月までに完成となると、その期間内に建てられるものは限られてしまう。木造で木を手刻みで一本一本みたいな悠長なことは言っていられないので、普通はプレカットの木材でパパッとやってしまうんですけど、今回僕らはいつもやっているような伝統的な造り方でやっているんです。とてもタイトなスケジュールでしたが、もうすぐ(※取材時)完成します。

—なぜそれができるんですか。
由利 見ていた人たちからも「ほかは四角い建物で四角い白い部屋が並んだようなものしかできないのに、何でこんなのができるんだ」というようなことを言われました。そう聞かれて思ったのは、限られた予算でもうけを出すために効率やスピードを求めるというのは、結局造る方の理屈に過ぎないんじゃないかと。効率よく建てるとか安く建てるとかは、子どもたちにまったく関係ないんですよね。
こども園というのは子どもたちにとっての建物なので、僕らはあくまで子どもたちを最優先に考えて造りました。子どもたちが0歳から5歳まで入るとして、とても多感なその時期を過ごす環境はものすごく大事なはずです。待機児童を減らすためにとにかく造って、100人200人収容できれば実績ができるからいいという考え方ではなく、その100人がその園で0歳から5歳まで過ごして、どういうふうに育つのか。そこは重視されていないように思います。
子どもたちが日常的にどういうものに触れ、どういう匂いを感じ、どういう風を感じるかということを考えていくと、僕が個人的に伝統的なことをやりたいからということではなく、地元の素材を使って地元の職人さんが建てるという結論にやっぱり至る。もしも子どもが減ってそこが幼稚園として使えなくなっても、デイサービスに転用したり、お店にしたり、何かしら使えると思うんですよね。そういう社会的なストックは残るので、長いスパンで考えたらそっちの方がいいんじゃないかと。僕は自分が造る建物が100年は持つようにしたいと思っているんです。
どっちが正しいとかではなく、大事にしているものが違うから、できるものが違うということであって、僕が違和感を持たないやり方をすると、そうなるんです。だからとても非効率的ですし、何で手刻みなんだと現場で言われることもありますが、何を大事にするかという基準はぶれないようにしたいと思っています。

—地元の素材を使って地元の職人さんと一緒に造るということを一貫してやられてきて、何か気付いたことはありますか。
由利 例えば僕が和紙を使いませんかと言ったときに、皆さん最初はクエスチョンマークが付くんですね。手すきの和紙をイメージできる方が少ないですし、普通の機械すきの紙と何が違うのかと思われる。だから必ず、和紙を作っているところへお客さんと一緒に行くようにしています。作り手さんに会ってもらって、すいているところを見てもらって、すいた紙を見てもらう。そうするとやっぱりお客さんの目が変わって、その素材との距離感が詰まるんです。カタログから選んだ何番のクロスというものにはなかなか愛着は持てないと思うんですが、このおばあちゃんがすいてる和紙をこの障子に付けるのかと思った途端、大事にしてくれるんです。
石も同じで、切り出しているところへ一緒に行くので、このおじいちゃんが切り出した石が玄関先に敷かれるんだと実感してもらえる。そうすればもう、朝に家を出るときも夜に帰ってくるときも「ああ、この石は…」と身近に感じてもらうことができる。でも何番のタイルという決め方だと、それが割れたとしても、同じ品番のものを頼んで終わりじゃないですか。だから、僕だけがいいなと思うだけじゃなくて、やっぱり共感してもらえるんだなということをこれまでの経験で実感しました。

とはいえ押し付けはしませんし、もちろん機械すきの和紙もタイルも選択してもらえるようにしていますが、結果的にはお客さんも自然素材を選ぶ傾向があると思います。まあ、フィルターを通って僕に来ている方たちだからだとは思いますけど(笑)
由利設計工房
地元の自然素材を使って、地元の職人さんの伝統的な技術による家づくりをお手伝いしています。その地域にある素材と技術でつくられるその地域の気候風土に適した住まいとはどのようなものなのかを模索する日々。
由利収
福島県郡山市生まれ。東北工業大学建築学科を卒業後、仙台市内の設計事務所に就職。2001年に独立し由利設計工房を開設。木造の個人住宅を中心に店舗の内装などの設計・監理を行う。
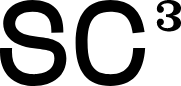
![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)








