知をひらく③ 後編|リーペレス・ファビオ(元 東北大学 大学院文学研究科 助教)

クリエイティブでいるためには、
「当たり前」を常に疑っていくことが大事
現在は「外国にルーツを持つ子ども」をテーマに、文化人類学を研究するリーペレス・ファビオさん。2020年に博士論文を基にした書籍を出版したファビオさんですが、どのような想いで書き上げられたのでしょうか。ファビオさんが常に抱いてきた社会への違和感についてもお聞きしました。
― 2020年に出版された『ストレンジャーの人類学 ー移動の中に生きる人々のライフストーリー』は先生の博士論文に基づいたものなんですよね。膨大な調査と編集作業を費やされたんだろうなと思うのですが、この本についてのお話を聞かせてください。
国際移動を繰り返しながら育つ子どもは、日本社会に限らず世界中にたくさんいます。その中の子どもたちには複数の文化や言語がある環境の中で育つ人がいて、僕と同じように特定の〇〇人とか、形容詞付きの△△系〇〇人という、国やエスニシティーの枠組みでは捉えきれない生き方をしているんです。たとえば、日本には外国にルーツのある子どもがいますよね。この言葉が意味するのは日本に帰ってきた帰国子女、日本に滞在する外国籍の両親を持つ子ども、そして国際結婚をした両親を持つ”ハーフ”と呼ばれる子どもたち。でも「外国につながる子ども」が指す言葉の意味って、もっと幅広いんです。全てに共通するのは日本と繋がりを持っていることですが、皮肉なのは国内で「日本にルーツを持つ子ども」とは絶対に呼ばれないこと。『ストレンジャーの人類学 ー移動の中に生きる人々のライフストーリー』では、国やエスニシティーの範囲だけでは言い表せないような人たちを「ストレンジャー」と呼んでいます。この本は、そのストレンジャーたちが大人になって、今日までの人生を振り返った記憶の中から「どのような生き方をして、どのように人と関わってきたのか」をまとめたものです。
― 確かに「ストレンジャー」に対する名前の付け方には疑問がありますね。本を出版する上で大変だったことはありますか?
そうなんです。調査に協力してくれた4人の方は、幸運にも色々な偶然が重なってタイミング良く出会うことができました。この本を書いているときは学部生や大学院の後輩、そして一緒に勉強していた後輩の人と議論を交わしたり、先生からアドバイスをもらったりしていました。僕の博士論文は、研究室で一緒に過ごしてきた人たちと議論し合う中でできあがったものなんです。そして、この本は博論に基づいていますが、さらにそれを出版するので正しい日本語を書かなければならないのがとても大変でした。文法はもちろんですが、誤字脱字の面でも気をつける必要があったので、当時院生だった人に協力してもらってすごく有り難かったです。彼女がいなければ書き上げられなかった。日本語は書き方一つでニュアンスやイメージが全く違うものになるので、今も論文を書くときには彼女にメッセージを送って言い回しなどをチェックしてもらっています。

― 他文化への理解が進んでいると言っても、些細なきっかけで差別が起こる場合がありますし、たとえばコロナ禍ではアジア人差別が増えていると聞きます。そういったときは、どうしても「ストレンジャー」ばかりが問い詰められる側に立ちやすいですよね。このような点を含めて博士論文を書くにあたって、他に気をつけたことはありますか?
これまで外国にルーツを持つ子どもたちや、海外移住をする子どもたちの研究で多く議論されてきたのは、アイデンティティについてだったんです。でも僕はどうしてもアイデンティティの問題には絞りたくなかった。なぜなら、常に僕も経験してきたことだったから。たとえば、オリンピックやワールドカップなどがあったときに「韓国とメキシコ、どっちを応援するの?」「どこの国を応援するの?」と聞かれることが多かったんです。「メキシコ人だから、好きな食べ物はやっぱりタコスでしょ?」とか、決めつけたような質問の答えからアイデンティティを見出そうとする人たちがたくさんいて、物心ついてから常に違和感を覚えていました。アイデンティティというものは、長期的にさまざまな事例を深く見ながら見出していくものなので、文化と同様に国や地域という範囲だけでは十分な答えは出せない。アイデンティティの面から研究しても、今までの例に当てはめ、どう当てはまるのか、反対にどう当てはまらないのかという議論しかできないんです。僕はそうじゃなくて、今まで浮かび上がってこなかったような事例を述べたくて、人との関わりに重点を置くことにしました。それが文化相対主義やコスモポリタリズムに共通する点があったので、そこから批判的に議論していくことに決めました。
― 調査方法として使われた「ライフストーリー」ですが、具体的にどのような方法なのでしょうか?
ライフストーリーは、文化人類学において個人の人生に焦点を当て、その人の生き方を語ってもらうことによって自分の人生、そして社会や文化を読み解こうとするものです。僕が専門にする文化人類学とは、人間を文化の側面から理解する学問です。つまり、文化をキーワードとして文化の多様性や共通性について考える分野です。そもそも文化はやっかいなものですが、僕の研究室の先生の言葉を借りると、人間のなすことやることは全てが文化と捉えられます。人類学の幅はとても広いのですが、僕の場合は「人の移動」に文化人類学からアプローチしていて、「その人たちは何を当たり前にして生きているのか」「彼らにとって”違い”とは何か」などを相手の立場になって理解を試みています。これは研究を始めてから気付かされたことなのですが、ライフストーリーを通して僕の身の回りで起きていた日常的な文化が当たり前ではないと分かったんです。自分とは違う人の話を聞くことで、自分自身について気づくことがたくさんありました。実は、このような「他者を鏡として自己を振り返る」ということが文化人類学の醍醐味でもあるんです。
― 調査協力者の生い立ちを聞く上では、どのようなことに注意して進めていましたか?
ライフストーリーでは、特定の個人が生まれてから今日まで経験してきた出来事についてインタビューします。ある体験を振り返って当時はどのような考え方や価値観を持っていたのか、それについて今はどのような意味があったと感じているのかなど、かなり奥深い話が聞けるんです。でも、ときには相手が誰にも話したことのないような恥ずかしい内容を聞くこともあります。もちろん、そういう話は簡単に質問して聞ける話ではないので、調査協力者と長期間にわたって深い信頼関係を築く必要があるんです。だから、基本的に調査は長期的なものになります。調査協力者から話を聞くときはインタビューというかしこまった形式を取っていましたけれど、ほとんどは一緒に食事をしたり、共通の友達と一緒に遊んだり、お酒を飲みに行ったりしていました。時には愚痴を聞いたり、相談したりしていましたね。友達を作るように雑談をする中でライフストーリーを収録したんです。文化人類学では、調査協力者とのありふれた雑談から得られる情報が重要な場合もあるので、インタビューをするときはあえて事前に質問は決めずに臨みました。聞き逃したものも結構ありますが、僕が収録した音声は1人当たり10~50時間にものぼり、文字起こしが本当に大変でした。最初は1時間分の音声を6時間かけて文字に起こしていたんですけど、だんだん慣れてきて3時間に縮めることはできました。
― 長期間にわたる調査で、しかも雑談をもとにインタビューされていたとすると、編集作業はかなり大変だったのではないでしょうか?
そうですね。インタビューで聞けた話は、たとえば5~6年の歳月を経て得られた情報でもあるので、1年前の話の内容と3年後に聞いた話を照らし合わせながら、書くときに時系列で整理していくんです。「この話とあの話がつながっていた」とか「あの話がこの話の続きになっている」というようなことはたくさんありますよ。長い時間を使って調査協力者と信頼関係を築いていくことが基本なので、同じ内容でも出会った頃に聞いた話より、信頼関係が深まっているときに聞いた話の方が濃い内容になります。やはり関係が深くなっている方が、相手は自分の価値観をストレートに語ってくれるんです。論文に書くときは自然な会話をしているように時系列で話をくっつけていて、編集した内容を相手に確認してもらいながら仕上げました。

― 本を読むと「折り合い」についてのお話が書かれていますが、どのような意味があるのか詳しく教えてください。
異文化と向き合うには「寛容」がキーワードになっていて、寛容を英語に訳すと「tolerance」になります。でも「tolerance」には、実は「我慢する」という意味もあるんです。つまり、寛容と我慢が一緒にされているということ。異文化に寛容になる、あるいは他人に寛容になるには、嫌々付き合うという見方もあるんです。それが分かってからは、他の国に移住してその社会のルールに従って暮らしたり、現地の人たちと関わりを持ったりする中で「折り合い」が重要なのではないかと思いました。その視点から異文化や相手を理解してみようと、本の中で「文化の折り合い」という言葉を使ったんです。折り合いをつけているから新しい言語を身につけられたり、理不尽に思えるような異文化の社会的なルールを自分の内面に落とし込めたりする。折り合いとは「郷に入っては郷に従う」ような感じです。
― なるほど。異文化や他者と折り合いがつかなかった場合は、どうすべきだとお考えですか?
本に書いてある内容でも、折り合いがつかない事例はたくさんありました。僕もそういう経験があります。僕はインターナショナルスクールの高校に通っていましたが、皆さんには色々な国の人が集まっている国際的な学校はお互いに寛容だというイメージがあるかもしれません。でも僕の学校はそうではなかった。僕の生き方はクラスメイトにとってもすごく複雑なものだったんだと思います。僕の両親はメキシコ人と韓国人だけど、インターナショナルスクールに通う前は日本の教育を受けていたから第一言語は日本語。しかし国籍を見るとメキシコになっているし、「ファビオ」という名前はイタリア人っぽい。だから次第に周りから不審がられるようになって、高校時代は誰一人友達がいませんでした。当時は「自分を周りが理解してくれないんだったら、僕も彼らのことを理解してやらないぞ」という気持ちになり、折り合いがつかないことがあった。でも折り合いがつかないことは文化の違いだと片付けられますが、それは個人の問題とも考えられるんです。僕が高校時代に友達ができなかったのは、僕の文化背景が相手にとって複雑で理解できなかったからだと感じていたのですが、もっと深く振り返ってみると僕自身の性格も関係していのではないかと思います。僕の、皮肉をよく言う性格が相手を遠ざける原因になっているんじゃないか、と。折り合いがつかなかったあとは「相手と関わりを持ち直そうかな」とか「過ぎ去ったことだから相手と会うこともないし、改めて関わるのは諦めようかな」とか、さまざまなことを考えて悩みました。でも、折り合いがつかない経験は、次に新しく人と出会う糧になります。そういう経験も踏まえて、異文化と他者を理解していく気持ちが大切だと思います。

― もっと文化人類学や先生の研究分野について知るために、おすすめの書籍などはありますか?
僕の研究は川上郁雄先生が提唱している「移動する子ども」学の系譜上にあると思っているので、彼の『私も「移動する子ども」だった』(くろしお出版)を手がかりに研究をスタートしています。あとは、加藤恵津子先生の『「自分探し」の移民たち-カナダ・バンクーバー、さまよう日本の若者』(彩流社)、金春喜さんの『「発達障害」とされる外国人の子どもたち』(明石書店)、川上郁雄先生・三宅和子先生・岩崎典子先生が編集された『移動とことば』(くろしお出版)もおすすめです。ちなみに、2022年4月には『移動とことば 2』の出版が予定されていて、僕も一章投稿しています。
― 文化人類学にとって、クリエイティブや創造とはどのようなところにあると思いますか?
クリエイティブや創造とは新しいことを生み出すということですが、文化人類学では新しい知見を出すことがそれに当てはまると思います。文化人類学は文化の側面から「人間ってなんだ?」という問いを解くことなんですけれども、これまでさまざまな理論を提唱して答えを出してきました。たとえば、国際移動をすることは人が貧困から逃れるために経済的な豊かさを求めて新しい場所に移動すると長い間信じられてきたのですが、そんな単純なものではないと研究者たちが明らかにしています。新しい理論では、個人の想像する生き方を実現するために憧れや願望が大きく影響していると提唱され、「ライフスタイル移住」という概念が生まれてきたんです。留学や国際結婚が良い例ですよね。このように我々人類学者の間でも、研究者が当たり前だと思っていることに対して常に懐疑的な姿勢を持ち、既存の理論を批判的に捉えることが必要なんです。自分が調査する人々と関わる中で新しい理論や知見をもたらしたり、もしくは今までの理論を覆して新しい理論を提唱したりするところは、クリエイティブだと思います。
― 最後に、今後考えている研究を教えていただけますか?
今興味を持っているのは、日系メキシコ人のこと。ただし、メキシコには日本にルーツを持つ人が住んでいますが、メキシコの民族に対する捉え方では形容詞付きのメキシコ人は存在しません。メキシコは移民国家ではあるけれど、たとえ両親のルーツが外国にあったとしても全員をメキシコ人と捉えているんです。でも今は言葉の利便性で「日系メキシコ人」という言葉を使っています。メキシコでは日系人の家庭の中に、自分の娘にだけ日本語の教育を受けさせるみたいなんです。他の日系人男性と結婚させたり、あるいは他の日本人男性と結婚させたりする習慣があって、そうすることで家庭の中での日本人性を維持、向上しているような現象がある。しかもメキシコには「セニョールクピード」と呼ばれる日系人の歯医者がいます。これを英語に訳すと「ミスターキューピッド」。何世代も受け継いで歯医者をやっている家系なのですが、患者のカルテとカルテを合わせてキューピッドをやっているんです。実際にセニョールクピードのところへ行って、自分の娘の見合い相手を探している家庭があるみたいですよ。なぜ日系人の女性だけがそんな目に遭わされるのかがとても気になります。この話は約10年前に他の日系人からたびたび聞くことがあって、まだ十分な調査はできていませんが、おそらく現在も続いていると思います。当時聞いた話をもとに、アイデンティティだけではなくてジェンダーの面からも研究したいですね。
前編 > 後編
リーペレス・ファビオ
2019年、東北大学大学院文学研究科で博士号(文学)を取得。2022年3月まで東北大学大学院文学研究科の助教として活躍。専攻は文化人類学。
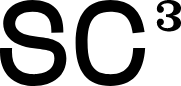
![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)








