クリエイターインタビュー前編|小泉 俊幸(カメラマン)

目の前のありようを、写真に残したいと思ったんです。
2018年からフリーカメラマンとして活動している小泉俊幸さん。東日本大震災を機に、写真で物事を形に表す仕事を志したという彼のルーツを遡るべく、ゆかりの地・気仙沼市をともに訪れてお話を伺った。
—もともとご出身は?
生まれたのは気仙沼市で、育ちは仙台市です。小さい頃に親の仕事の都合で引っ越してから、ずっと南仙台ですね。母方の祖父母が気仙沼に住んでいるので、今もちょくちょく訪れますが。
—昔から「カメラマンになりたい」と思われていたんですか?
いや、小学校の卒業文集では、将来の夢をサラリーマンと書いた記憶があります(笑)。親が趣味でフィルムカメラをやっていて、たまに借りて撮ることはあったのですが、将来的にそれを生業にしたり、自己表現をしたりしたいとは思っていなかったですね。
—そこから表現の道に進もうと思ったのは、どうしてだったのでしょう?
実を言うと、はっきりとした意志があったわけではなくて。高校卒業後は尚絅学院大学総合人間科学部表現文化学科(2019年から再編成)に進学したのですが、最初は実家から近いというぐらいの理由で興味を持ったんです。でも、調べていくうちに文章や映像、地域文化にまつわる表現を柱にした学科があると知り、おもしろそうだなと。映画も好きでそれなりに観ていたし、一番自分の身近にある表現かなと思ったので、映像の分野を選択しました。
—出発点は映像だったんですね。その後、写真を撮り始めるまでには、どんな経緯があったのでしょうか?
大学2年時の春休みに東日本大震災が起こったんです。気仙沼も大きな被害を受けて、身内はみんな無事だったけれど、親戚の家は津波で流されました。その当時僕は仙台にいたのですが、たまたま手元にカメラを持っていて。自分が表現を学ぶ上で、こういうときに取った行動が、これからにつながっていくんじゃないかと思ったんです。そして、震災から1ヶ月後くらいに気仙沼を訪れて、いろんな場所を巡りながら写真を撮るようになりました。

—当時感じていたことを伺ってもいいですか?
同じ被災県内でも、やっぱり内陸と沿岸部で状況は違うなと思っていました。僕の住んでいる地域は停電や断水で済んだけれど、沿岸部は全然そんなものではなかったので。震災後に撮影した写真は、最終的に卒業制作で本にまとめたのですが、そのタイトルは『温度』なんです。地域ごとに異なる様相や雰囲気の差を意識して付けました。当初は被災地に近づくことすらできないような、もどかしい感覚もありましたね。現地にも、はじめはコンパクトなカメラを持って行っていました。
—自分の姿勢や行動を問われるような感じはあったかもしれませんね。
沿岸部の人からすれば、カメラを持って地域に立ち入るのは、実際、野次馬と変わらなかったと思うんです。でも途中から、個人単位でもいいから、何かしらを残さなきゃいけないんじゃないかと強く思うようになって。そこで踏ん切りがついてからは、ちゃんとした機材で撮るようになりましたね。今となっては、自分の行動は間違っていなかったと思います。やっぱり、以前の様子がわからなくなってしまった場所もたくさんあるので。
—意味のあることだと思います。本にまとめようと考えたのはいつ頃だったんですか?
1年半ぐらい撮り続けていたら、だんだんと枚数も溜まってきて。たぶん数千枚はあったと思いますね。それで、卒業制作をつくる時期になって、自分が今まで学んできたことを形にするならと考えたんです。映像がメインの研究分野ではありましたが、広く視覚文化を学んでもいたので、写真をまとめた本をつくろうと決めました。

—卒業後の歩みについてもお聞かせいただければと思います。
一度、建設機械のレンタル企業に営業担当として就職したんです。工事の中心は沿岸部だったので、被災地にもよく行っていましたね。でも、学生時代に自分が取り組んでいたことを振り返ってしまうというか。目の前のありようを写真に残そうとこだわって、本にまとめたことが忘れられなくて。この後の人生を考えたときに、やっぱり写真で物事を形に表す仕事がしたいと思うようになっていったんです。それで、1年と数ヶ月で退職し、日本デザイナー芸術学院仙台校の写真映像科に入学しました。
—その頃はどんな写真を撮っていたんですか?
1年次から2年次の進級制作で『直(すなお)』という作品集をつくったのですが、これはビルの窓や建物の輪郭など、とにかく真っ直ぐな線で構成された風景をまとめました。寄ったり視点をずらしたりして、被写体を直線で構成されたイメージのようにとらえて撮っています。

—「真っ直ぐ」というテーマはどのように導き出されたのでしょう?
撮影していく中で見出していきました。これを制作する以前から、カメラを持って街をぶらぶらしながら、なんとなく写真を撮ってはいたんですね。そして、ある程度枚数が溜まってきたときに、真っ直ぐな線で構成されたものが結構あるなと傾向が見えてきて。そこから、だんだんと「いいな」というポイントがわかっていった感じです。カメラを持っていなくても携帯で場所をメモして、後日撮りに行くこともありましたね。あとは、卒業制作の『映ル』。これも同じように、撮り溜めた写真を見返す中で、反射しているものが多いなと気づいて。

—どちらも、写っているものの即物的な特徴を引き出したタイトルが印象的です。
撮るときは、見ていて「おもしろい」「なんか気になるな」という感覚にしたがってシャッターを切っています。だからこそ、撮った写真を集約したときに、その時々の関心がテーマとして浮かび上がってくるのかもしれません。『映ル』の中では、この手すりの写真が一番気に入っているんです。撮影したときは空が本当に真っ青で、その色が全面に映っていて。手すりというより“もの”みたいに見えるというか。質感が好きですね。

—何気ない光景ながら、すごく非日常的なイメージに受け取れる不思議な作品ですね。小泉さんは、写真のどんなところにおもしろさを感じますか?
僕は街のスナップを撮ることが多いのですが、カメラマンによっては、この位置に人が来て、こういう光が入ってと、思い描く構図を撮るために粘り強く待つ方もいて。もちろんそのつくり方も真っ当ですし、独特の魅力があります。一方で、僕は一期一会というか、その場、その瞬間に立ち現れて、なおかつ自分が「いいな」と感じる風景が撮れるとベストかなと。そういう向き合い方は大切にしていますし、おもしろいところだなと感じますね。
取材日:令和元年10月3日
撮影協力:アンカーコーヒー内湾店
取材・構成:鈴木 瑠理子
撮影:豊田 拓弥
前編 > 後編

小泉俊幸
1991年宮城県気仙沼市生まれ、仙台市育ち。尚絅学院大学総合人間科学部表現文化学科、日本デザイナー芸術学院仙台校写真映像学科卒業。広告スタジオ勤務を経て、2018年よりフリーランスのカメラマン/アシスタントとして活動している。
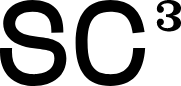
![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)








