クリエイターインタビュー前編|千田優太(アートコーディネーター・パフォーマー)

人が集まり、新たな面白いことが生まれる「場づくり」
東北における舞台芸術の企画や制作を行なうアートコーディネーターでありながら、コンテンポラリーダンスのパフォーマーでもある、一般社団法人アーツグラウンド東北 代表理事の千田優太さん。地域と文化・芸術がお互いに理解し発展できる「場づくり」を続ける根底には、面白さを追求する千田さんの誠実な人柄がありました。
ー 千田さんは普段、どんな活動をされているんですか?
そうですね。一般社団法人アーツグラウンド東北という団体を2016年に立ち上げて、舞台芸術の企画をつくったり、地域とアーティストを繋ぐコーディネーターをしています。生業としては「放課後等デイサービス」という障害のある子どもたちが通う児童館職員です。パフォーマーとしての活動も大学在学中から続けています。
ー 幅広く活動されていますね。
アーツグラウンド東北では、『ダンス幼稚園』と次代を担う東北の文化的コモンズをつくる『せんだいみやぎ文化的コモン部』という事業を展開しています。
『ダンス幼稚園』は2012年〜2019年までイベント企画として開催してきたのですが、今年度から事業化しました。事業内容は『beatpia(ビートピア)』と『子どもの視点、アーティストの視点』の2つです。
『beatpia』は、劇場へ足を運びにくい幼児や保護者でも、劇場で行われるような本格的なダンスを気軽に鑑賞・体験できる企画なんですが、今年度からは音楽の要素をプラスしました。現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、無観客公演へ変更しています。
また『子どもの視点、アーティストの視点』では、向山こども園(仙台市)とわだつみ保育園(塩竈市)にアーティストが滞在制作をするアーティスト・イン・レジデンス(以下、AIR)を行なっています。職業としてのダンサーの仕事を子どもたちが間近で見る機会と、ダンサーが子どもたちから刺激をもらいながら作品づくりに専念できる場を提供する事業です。しかし、こちらの事業もコロナの影響で内容を変更していて、向山こども園は動画による交換日記の実施、わだつみ保育園のAIRにおいては、滞在日数を縮小中です。

ー 『せんだいみやぎ文化的コモン部』の取り組みについても教えてください。
「文化的コモンズ」という、地域の共同体の誰もが自由に参加できる入会地のような文化的営みの総体を示す言葉があります。せんだいみやぎ文化的コモン部はそれに関心のある人たちが「文化・芸術の政策を自主的に考え、つくりながら学ぶ場」として、月に一度(木曜日)開催する部活動のようなものです。部員は随時こちら(入部届)から募集中です!
部活内容は、部員の中から立候補制で1日部長(進行役)を務め、自身が興味のあるテーマを話し合います。また、専門家やアート関係者をゲストにお招きし、講演いただいた内容を参加者全員でディスカッションを行ないます。この場では「他者の意見は否定しない」「専門用語でわからないことは必ず聞く」「他者の発言は最後まで聞く」ということを大切にしています。
ー それはなぜですか?
事業初年度に、コーディネーターや専門家を集めてフォーラムを開催したのですが、専門家が専門用語を並べて話し合っていることに違和感を感じたからです。私がその場をつくったんですけど(笑)
地域の共同体の誰もが自由に参加できる文化的営みをつくろうとしているのに、新たな「文化的コモンズ」となり得る地域の方々が参加していないことに気づいたんです。そこから軌道修正して今年度は『せんだいみやぎ文化的コモン部』と銘打って事業を改めました。これからは地元にある魚屋の亭主とか専門家ではない地域の人が参加してもらったほうが面白くなるし、必要なことだと思っています。

ー どちらも面白い事業ですね。はじめたきっかけは?
大学4年生の時に留年した時の出来事ですね(笑) 少し話が脱線するのですが、話していいですか?
ー ぜひお願いします(笑)
私は宮城教育大学出身で、保健体育を専攻していました。部活はサッカーをやっていたのですが、専攻科の必修授業で創作ダンスと出会い、間違った道へ(笑)サッカー部を辞めて、のめり込みましたね。それで当時、コンテンポラリーダンスのダンサーが全国各地を巡業するという『NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク (以下、JCDN)』が主催する公演があり、その仙台公演で代表に選ばれたんです。それで大学を卒業できず、1年長く勉強することになりました。ただ、その公演を機にJCDNの方々と親睦を深めることになり、のちに 三陸国際芸術祭 を手伝うことになりました。

ー そのまま芸術祭の仕事に就かれたんですか?
いえ。大学卒業した後は、5年ちょっと東京に就職していました。小学校の教諭を3年間した後、飲み屋さんをやってみようと思い、2年程度ですが東京の飲み屋さんで働いていました。2010年に仙台へ戻り、スキー場の求人を見つけて「ちょっと寄り道しよう」と住み込みで働きました。実はスキー場のペンションを経営するのが夢だったときがあり、昔の夢をちょっとだけ体験しようと思ったんですが、そこで東日本大震災が起きて。
震災後、知り合いのアーティストや舞台芸術関係者が、子どもたちに向けたアート支援活動を行なう『ART Revival Connection TOHOKU(以下、ARCT)』を立ち上げたので、コーディネーターとして携わりました。この時に、表現者側にいるよりも人や地域にアートを繋げることの楽しさに目覚めてしまったんです。その後は、三陸国際芸術祭の事務局をやらせていただいたり、現在、事業として行なっている『ダンス幼稚園』などの活動を実行委員会ベースで実施してきました。

ー 飲み屋さんからコーディネーターへの転身。振り幅が大きいように感じますが、共通して実現したいことがあったのでしょうか?
仙台の春日町にあった居酒屋『あべひげ(※)』のような「人が集まり、新しいことが生まれる場」をつくりたかったんですよね。当時はそこまで確信を持てていなかったが、ARCTで復興支援に携わったことでその想いに気づくことができました。
(※)1989年創業。美術・音楽・演劇・ダンス・ラグビー・映画などの多岐にわたる人々から交流の場として愛された居酒屋。2008年年末、店主である阿部立男さんが急逝し、2009年に閉店。阿部さんは、1984年 舞踏制作集団「南斗六星」設立・主宰。大駱駝鑑・大野一雄氏・田中泯氏らの仙台公演を手掛けた。
ー 千田さんらしいですね。現在も事業を行ないながら、パフォーマーも続けられているとのことですが、どんな作品を作られているんですか?
やりたい時にやる程度ですよ(笑)『それでも彼女は笑っていた(2012年)』では、ワークショップを行なう際、よくガムテープに名前を書きますよね。その要領で、自分の名前や家族・友人の名前、好きな食べ物・場所など自分を構成するあらゆる名前を書き、それを身体中に貼り重ねて脱ぎ捨てるというパフォーマンスをしました。

ー 最近では、同様の手段を用いた動画作品もありますね。
「フラワーオブライフ」という作品です。漫画『西洋骨董洋菓子店』原作者・よしながふみさんの別の作品で『フラワー・オブ・ライフ』という、白血病を克服していく男子高校生が学校生活を送る話があるんです。この漫画にインスピレーションを受けて、実写化したいと思いました。
作中で「He died in the flower of life.(彼は若い盛りに死んだ)」というフレーズが、友人の死と重なったんですよね。撮影を手伝ってくれた友人たちも亡くなった友人と遊び仲間でした。なので撮影中はまだ生きている感じがあり、お盆に帰省してきたような久しぶりに会えている感覚を覚えました。それは今でも思います。
ー なぜ、貼って脱ぎ捨てる行為をはじめたのですか?
このパフォーマンス手段は『それでも彼女は笑っていた(2012年)』からはじめたもので、亡くなった祖母に捧げる作品でした。この作品タイトルも漫画『宇宙兄弟』から引用したものです。この漫画に登場する「シャロン博士」という、難病ALSと闘病する女性キャラクターが祖母とリンクしたんです。
私を構成しているものを脱ぎ捨てた後で自分に何が残るのかを見てみたかったのと、そのありのままの「今の自分」を亡くなった身近な人に見てもらいたいと思いました。

ー 脱ぎ捨てる行為は、自分を構成する社会と向き合うために必要な行為だったんですね。
そうですね。地域と関わるアーティストには、そこで仕事をしたり生活している人がいることを蔑ろにしてほしくないし、地域の人には文化・芸術が生きるために必要な存在であることに耳を傾けてもらいたいです。どちらか一方だけが大事なのではなく、両者に対して関心を向けることが必要だと思っています。

千田優太(ちだ・ゆうた)
1980年宮城県塩竈市生まれ。アートコーディネーター・パフォーマー。宮城教育大学卒業。2011年〜2014年ART Revival Connection TOHOKU(現ARCT)事務局を経て、2015年に同代表を歴任。2014〜2018年『三陸国際芸術祭』フェスティバルマネージャー。2016年『一般社団法人アーツグラウンド東北』設立。小学校教諭・コンテンポラリーダンスの経験を活かし、東北における地域と舞台芸術のための企画・制作を行なう。
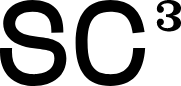
![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)







