ライターバトン -21- 「煮詰まり過ぎて、今」

仙台を中心に活躍するライターが、リレー形式でおくります。前任ライターのお題をしりとりで受け、テーマを決める…という以外はなんでもアリの、ゆるゆるコラムです。
煮詰まり過ぎて、今
思い起こせば、小学6年生の学芸会。宮沢賢治をテーマにした歌やダンス、演劇などの総合舞台芸術を企画した先進的な先生から、「注文の多い料理店」の脚本を依頼された。これが、物書きとして意識した原初だったと思う。主人公である若者2人に自らを重ねながらセリフを考え、当然、本番で演じられるのは私しかいないだろうと確信し、渾身の自信作を完成させた。しかし、実際に配役されたのは、物語の終盤、山猫の魔の手から逃げてきた若者たちを見つける端役の猟師。セリフは、「旦那ぁ、旦那ぁ、なしてそんな格好しているんだべか?」の滑稽な一声。それでも、原作には無い方言の言い回しを加え、田舎臭漂うコミカルなキャラクターが劇を締めくくるという、独自の演出が思いがけずウケて、会場は笑いと拍手で大盛況。自分の書いた物が、これほどまでに観客の心を掴んだという衝撃にたまらない恍惚感を得られたのは、まだ誰にも話していない。
物語に没頭し過ぎる悪癖は、中学生の時に いわゆる“おたく創作”の沼にどっぷりと足を踏み入れたり、高校の放送部で大映テレビドラマを模倣したような甘酸っぱい世界観でラジオドラマを作ったりと、あまり知人には知られたくない若気の至りを繰り返すことになる。大学で国文科を専攻したのも、物語の海に身を委ねる愉悦を求めるがゆえ。卒業論文に、中古文学ではそぐわない突飛なテーマを設定してしまい、真夜中に友達を呼びつけて清書の手伝いをさせるほど提出が遅れ、普段は温厚な担当教授に鬼の形相をさせたのも苦々しい思い出だ。
物語の病をだいぶこじらせたまま社会人となり、紆余曲折を経て20余年。気づけば、小説家や物語作家ではなく、実直に広告原稿を手掛けるライターとなった自分がいる。あれほど創作の世界を夢みていたイタい妄想少年だったはずなのに。それは、自分が書いたもので、人の心が動く手応えを知ってしまったから。最初の一歩となったのは、アルバイト気分で書いた、たった120文字足らずのレストラン紹介記事に、取材先の店主からお礼の電話が届いた素直な喜びだったと思う。その先を求めて、がむしゃらに記事を書き重ねる日々。もちろん、失敗して怒られることも数知れず。そうしてこの仕事は、相手の真意を測る取材の面白さと、意図ある言葉を繰り出すことで、読み手の印象や行動原理を大きく左右させるほどの魔力を生むことに気づく。そのために求められる素養が、筆力、知識、ひらめき、発想力、センス…と、途方も無いが。
最近、後進の指導が社内業務のひとつになりつつあるが、プロとしての技術やセオリーについて尋ねられてもピンとこない。取材や聞き取り、下調べでたくさんの判断材料を詰め込み、頭の中でぐつぐつと煮詰めていく。そして、どのくらいの分量でどんな味付けにすれば受け取り手に響くか、熟考を重ねて原稿を仕上げるのが、やっと自分のスタイルとして確立したような感がしている。20代の時に、TwitterのようなSNSがあったら、もっと直感的な書き手になっていたかもしれない。東日本大震災後、東北各地を訪ねる仕事が増えたことも、ライターとしてのスタンスに大きく影響しているだろう。何にしろ、経験を経るほどに抱えるものが多くなったのか、ますます遅筆がひどくなってきた気がする。猛省。
いつか、自分が考えたセリフで喝采を浴びた小学6年生の舞台のように、渾身の作と誇れるコピーを世に送り出し、社会を動かすほどの手応えが得られる栄光の瞬間を…。そんな果てしない野望を抱きながら、今日も〆切間近の原稿に、いつも通り煮詰まっている。
次回
次にバトンを託すのは、出版社時代の先輩であり師匠、そして今は呑み友達の、愛猫の名前を屋号に掲げるナルトプロダクツ・佐藤隆子さん。「ま」から始まるタイトルで含蓄の深いコラムを書いてくれるでしょう。
-20-「魅力は理不尽さとともに」> -21-「煮詰まり過ぎて、今」> -22-「まだ物心ついていないので」

小杉一高
大学卒業後、テレビ番組制作会社のAD、仙台市内の出版社で編集の経験を経て、現在は広告制作会社の株式会社創童舎に所属。コピーライターの一員として、さまざまな広告や出版物を手掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
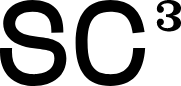
![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)








