クリエイターインタビュー前編|明才(木版画家)

想像を視覚化する喜びの共感が、返り咲くほどの実践連鎖
東北の魅力を視覚化(ビジュアル化)する、木版画家の明才さん。創作意欲が湧かず蒸発寸前だった明才さんは、怒涛の実践連鎖によって想像を共有する喜びを知り、再起を果たす。その背景には、地域愛が溢れる同級生や奇特なパートナーからの刺激が原動力になっていました。
ー 東北をビジュアル化することが得意な明才さんですが、本当にたくさんのバリエーションで作品を手がけていますよね。
今こうして様々な作品をつくることができているのは、本当に有り難いことで「たまたま」の積み重ねなんです。現在は木版画の作品をベースに冊子の挿絵や表紙をはじめ、舞台チラシや衣装美術、ウェブサイトに掲載するイラストなどを手がけています。ウェブサイトは「心に届く手紙屋さん」という手紙を代行で描いてくれるところから依頼を受けました。この方も私と同じ名取在住の方でしたね。舞台は今回取材の紹介をしてくださった俳優 芝原弘さん主演ミュージカルの物です。
でも、本当にこれまでいろんなことがあったんですよ。名取の実家を出てからは、尋常じゃない早さで人生が動き出しました。笑

ー 仙台に移住されたのはいつ頃ですか?
仙台に移住したのは東日本大震災があった2011年の2月です。それまでは実家暮らしで映画館の仕事をしていましたが、年中無休なうえに少人数で運営していたので心身ともに壊れてしまい、何もできない状態が続いていました。しかし2009年、私が30歳のときに気仙沼市のリアス・アーク美術館から企画展「N.E.blood12」に声をかけていただき「これは頑張ってやりたい」と思い、作品を展示させていただきました。
その後「せっかくの人生だから、失敗しても好きなようにやってみよう」と考え、仙台に引っ越した後すぐに震災がありました。単発で版画の依頼はいただいていたけれど無計画なうえに震災が起こるはで、当時は日々の生活を回すことに意識が回っていましたね。
またこの頃は、いろんなクリエイターや音楽関係の方などが家に泊まりにきていたのでその方たちの話を聞くことが、版画をつくることよりも面白かったです。

ー クリエイターたちとの関わりの中で、心境の変化はありましたか?
その当時の私を知る友人からは「めちゃくちゃ拡大してたよ」と言われます。人間関係は広がるし、気持ち的にも大きくオープンになっていましたね。ただ、版画の仕事をいただけても継続的に仕事を回すためのアイディアが私にはなく、お金はなくなっていき「あーもうここまでかー。人生終わりかー。私生きるの下手だったなー」って自信を失くしていました。
そしてついに「山に溶けて、蒸発するかー。蒸発って溶けることだったんだなー」と思いはじめたとき、私の前に奇特な人が現れたんです。
「もうちょっとあなたに生きていてほしいな」って、その人に言われたんです。それで私も「あなたのことすごくいいと思っている」と告白し、そのまま結婚しました。笑

ー 急展開ですね!
そうなんです。結婚する1年ぐらい前に「こいついい奴だなー」という急激な出会いがありました。優しいのはもちろんなのですが、なんか「面白いこと考えて、面白いことやってるなー。こういう人材は育ったほうがいいな」と思いました。それに10歳年下だから期待感にワクワクが止まらなくて。親目線ですかね?笑

ー ご結婚されたのはいつですか?
2013年に籍を入れて、その一か月後に妊娠が分かりました。もう怒涛の生活ですよね。あまりの展開の早さに、夫も結婚した事実に驚いていたくらいです。私には結婚の気が全くなかったので、とにかく周りの誰もが驚いていましたね。
2014年に出産して子どもが3歳になるまでは、版画作品はつくることができなかったです。
ー 子育てや生活に追われてしまったのですね。
紙を前にしても何も思い浮かばなくなってしまい「もうつくれないんじゃないか」って諦めていました。子どもの頃は頭の中に浮かんでくる何かをとにかく紙に描いていたので、私の人生でこれは異常な事だったんです。
でも他の作家さんには同じ境遇でも「母になった記念個展」を開催する方もいて「すごいなー。作家ってそういうものなのか」と感心するばかりで、私はその体力と気力を持ち合わせていなかったんです。
でも、これまで関わってくださった皆様に申し訳ないという気持ちはずっと心に引っかかっていました。特に、リアスアーク美術館の方には「10年は続けてくださいね」と応援してくださっていたので、どうにかしてこの状況から抜け出したかったです。

ー そこから息を吹き返すことができたのは、いつ頃だったのでしょうか?
子どもが3歳を過ぎて保育園を探しはじめたときですね。三浦農園(名取市)でセリ農家をしている同級生の三浦隆弘さんから、セリのラベル依頼をいただいたのがきっかけで創作意欲が徐々に湧いてきました。以前にも、三浦さんが地元の小学校と協力してつくった紫黒米を記念品になるようにと、私にラベルのお手伝いをさせてくれたこともありました。
ー 同級生の存在は有り難いですね。三浦さんとはそれまでも連絡を取り合ったりしていたんですか?
そんなことはなくてですね。学校でも会話した記憶がないくらい。笑 なので、連絡もそれまではとっていなかったんですが、メディアに私のことが取り上げられたのを見てくれて連絡をくれました。リハビリのつもりでゆっくりやってみようとお仕事をさせていただいたのですが、ここから怒涛の「名取実践」がはじまりました。笑

ー 「名取実践」! 一体何が起こったんですか?笑
セリのラベルが完成すると、三浦さんが「閖上に佐々木酒造店があってね、そこの甘酒のラベルが欲しいんだ」と、ひと息つく間に次の仕事を紹介してくださって。さらに、甘酒のラベルを制作しているときにも「名取市観光物産協会ってところが、法被のデザインを…」 「名取の熊野那智神社でも法被を…」という具合に、地元での仕事を立て続けにいただけることになったんです。
ー 三浦さんは明才作品の虜になってしまったんですね。
三浦さんに限らず40〜50代の男性に人気があります。木版画の作品をたくさんの方が「かわいい」と言ってくれるのですが、実際に仕事を依頼してくださるのは男性なんです。おじさんが求める「かわいい」をつくっているんでしょうね。

ー 確かに木版画の風合いは日本食や文化と相性がよく、できあがりのイメージがしやすい気がしますね。そして「名取実践」後は舞台のお仕事をされたそうですが、どんなことをされたんですか?
そうなりますよね。笑 これまで舞台関係仕事はもちろん、それほど演劇を観たことも多くはありませんでした。なので「演劇ってすごいなー」と観客側でしかなかったのですが、人伝に私のことを知ってくださった舞台のプロデューサーから、衣装と舞台美術を依頼されました。しかし仕事量が打ち合わせ途中から増えていき、出演者の衣装美術は全員分、さらには舞台上のスクリーンにもイラストを描くことになったんです。衣装美術は着物をリメイクしたり、ちょっとしたぬいぐるみ作品を制作したことしかなかったので「舞台仕事が未経験の私で本当にいいのかな」って不安になりましたね。笑

ー 舞台イメージの共有をして製作に取り掛かるのに、どんな準備と時間が必要でしたか?
舞台の公演が2020年2月末だったので、つくりはじめたのがその年明けから。年が明ける前は、色々イメージを膨らませたりとかしてました。ちょうど東北歴史博物館で古代蝦夷の特別展が開催されていたので観に行ったり、本や資料を読んだりしていました。最初の打ち合わせが2019年10月だったため、舞台の準備としてはかなりキツキツのスケジュールで、4, 5ヶ月はずっとこの作品をつくり込みましたね。
ー それだけ制作に入り込むと、他の依頼がきたら大変じゃないですか?
本当にそれは思います。でも私がこうして実践に耐えられるようになったのは、夫が私のマネージメントをしてくれているお陰なんです。
ー 羨ましい限りです。
夫はよく「アーティストが自分で交渉したり、スケジューリングしたりするのは無理だよ。アーティストはつくることが仕事なんだから、それ以外のことに時間と労力を割いてるのは勿体無い」と言っていて。 マネージメントができる人が入ると、アーティストはもちろん依頼者も何をどこまで頼んでいいかが明瞭になって、双方ともにいいことしかないんです。

ー アーティストにはマネージャーが必要ですね。
そうですね。ただアーティストもマネージメントができる人自身も、その必要性に気づけている人が少ない気がします。仕事を効率良くスムーズに進めるために、調整を円滑にできるマネージメントが大切だということをいろんな人が分かってないと、職業として成り立たないしマネージャーが育たないですよね。目立たないし評価されにくい仕事だけど、私のようにものづくりに集中したい人たちを成功に導くには必要な存在だと思います。
なので、マネージャーが欲しい人はもっと声を大にして求めたほうがいい。笑
ー 私もほしいです。笑 ここまで作品について伺ってきましたが、仕事を依頼されるようになって気づいたことはありますか?
「私は依頼に応えるのが結構好きなんだな」ってことですかね。
子どもの頃はお絵かき遊びで、友達から猫とかライオンを描いてほしいとかトラを描いてほしいと頼まれて描いてたんですね。実はトラってトラ猫にならないように描くのが難しいんですけど私にはそれができて、友達が喜んでくれると嬉しかった記憶があります。こういう感覚はずっと忘れていたのですが、作品の依頼がいただけるようになって思い出すことができました。

それに依頼をくださる皆さんは、いろんなことを考えてるんですよね。三浦さんはセリとそれを含む暮らしだとか土地の歴史だったり、民俗的なことだったり。舞台のプロデューサーの方も膨大なアイデアが湧いてくる人だけれど、それを視覚化(ビジュアル化)することができないので、私がそこを補うことができたんだと思います。私は依頼者の方々とイメージを共有しながら作品をつくり出すことに、喜びと面白さを感じるようになりました。
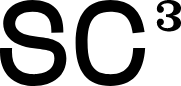
![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)









