クリエイターインタビュー後編|福原悠介(映像作家)

語り手である対象と聞き手である自分とを行き来しながら、どういう記録のかたちがありうるか考えていきたい。
40年近く続いた仙台の映画館の記録集では、映像ではなく本としてまとめるなど、ひとつの手法や表現に捉われずさまざまな記録の在り方を試みている福原さん。インタビュー後編では、そうした「記録すること」のベースにある考え方とともに、仙台で制作を続けることの面白さや難しさ、今後の活動について伺いました。
ー 2019年に刊行された記録集『セントラル劇場でみた一本の映画』では、映像だけでなく、本というかたちで記録することを試みていらっしゃいましたね。
クリスロードの角にあった映画館「仙台セントラルホール」が閉館すると聞き、友人たちと何かのかたちで記録を残したいねという話になったんです。一緒に活動していたのが映画館の元スタッフだった村田怜央さんで、彼がビデオカメラを持って閉館前の劇場を撮ってみたりしたんですがいまいちしっくり来なかった。どういう表現や手法を取ればセントラルのことを記録できるのだろうと試行錯誤し、結果、映像ではなくこうしたエッセイ集のような記録ができあがりました。

ー それぞれのなかにある鑑賞体験や記憶を記したエッセイを通して、セントラルという映画館のすがたが浮かび上がってくるのが印象的でした。
映画館の記録というと、一般的には年表や支配人インタビューがあったり、館内のグラビアページがあったりなど、はじめは郷土資料的なものをイメージしていたんですがなんだかしっくり来なくて。それだけではセントラルを記録したということにはならないと思ったんですね。そもそも映画館ってどんな場所だろうと考えたとき、映画館はいつでも、どこでも、何度でも上映される「映画」という作品が一回きりの経験になる場所なんだと気づいたんです。なので、映画館を特別な場所として記録するのではなく、むしろどこでも観られる映画をあの場所で観たという経験について書いてもらうことで、映画館のような記録を生み出せるのではないかと思い、いがらしみきおさん、伊坂幸太郎さんなど在仙の作家から、常連さんや支配人、元スタッフや元市長までさまざまな方に、かつてセントラルで見た映画を一本選んでいただき、それについてエッセイを書いてもらいました。
ー 本を読んだ方からはどんな声が届いていますか。
この本には仙台という町にあった映画館の話が書かれているけれど、一つひとつの作品をよりどころに、仙台に限らないさまざまな土地での自らの映画体験とつながったという声も多く、今はもうなくなった地元の映画館を思い出すとか、自分がかつて通っていた映画館にあんなお客さんがいたなとか、パーソナルな記憶と結びつくという話をよく聞かせてもらいました。
映画は、いつでも、どこでも、何度でも上映できるから、同時多発的に複数の土地で同じ映画を観ている人たちが存在しているけど、それぞれが作品を観たという経験は唯一のもので、その両方が成り立つのが「映画」なんだということを本の制作を通して改めて実感したんです。

ー 刊行後は、このインタビューの取材場所である「曲線」をはじめ、各地の書店でトークイベントを行うなど、記録をどう届けていくかについても積極的に取り組んでいらっしゃいましたね。
本をデザインしてくれたデザイナーの伊藤裕さんが全国各地の書店とつながりがある方で、声をかけてもらいトークイベントを企画しました。本自体は仙台の記録ですが、結果的にほかのどこかの土地の映画館ともどこかつながるような内容になりました。ただ、そのことは本を置いてもらうだけではなかなか伝わらないので、実際に色んな土地を訪れて直接届けるのが良いと思ったんです。話すことは得意じゃないので、緊張して吐き気をこらえながらでしたが…(笑)。映像か本かという記録のかたちもそうですが、どうやってつくり、どう届けるのか。そうしたことを含めて「記録すること」について考えることができた機会だったと思います。
震災後、さまざまなかたちで記録が生まれていきましたが、単に記録するだけだと届かないこともあるし、ただ撮影しただけでは何も映らないこともある。メディアテークが行う「3がつ11にちをわすれないためにセンター」の活動もそうですが、記録するだけでなく、それらをみんなで観て語らう場をつくったり、そうした時間まで含めて考えていくことが必要だと感じます。震災後の仙台で、広い視点で記録という行為を捉えている人たちに出会うことができた経験がやはり大きくて、この本もそんなふうになればいいなと思ってつくりました。
ー 映像と本と、表現方法は違えど、「訪ね聞き、記録する」活動のベースにはそうした想いがあるんですね。
記録する対象とそれを受け取る聞き手の自分とを行き来しながら、どういう記録のかたちがありうるか考えていく。記録すること自体よりも、そうした部分を考えることを自分の仕事にしていきたいと思っています。撮影ができるので結果として映像作品になることも多いけど、その一歩手前で試行錯誤しながら、その時々でできることを考えていきたいですね。

ー 現在は仙台にお住まいですが、仙台で制作することの面白さや難しさについて普段感じていることはありますか。
僕の仕事は撮影、録音、ディレクションなど多岐に渡っていて、いわゆる何かのスペシャリストではないんです。東京の商業映画の現場ではカメラマンが録音も担当することはあまりなくて、基本的には分業しています。仙台では予算が十分にある案件は少ないので、良くも悪くも一通りの作業をひとりでやらなければいけない場合も多い。でも、そうして複数の領域を横断しながら制作できるぶん、自由度も高くなれるんです。分業制だと制作パターンもある程度決まってきてしまうので、横断的に表現方法を考えていけるのは仙台ならではなのかなと思います。個別のスキルは専門家にはかなわないけど、仙台ではもう少し別のやり方でゆるくひらかれていくところがあると思うので、そういう人が仕事をしやすい場所なのかなって。
あとは地方にいても制作しやすい環境が、ここ10年ぐらいでより整ってきましたよね。撮影機材もだんだん安価になってきていますし、ネットのクラウドサービスも充実しています。

ー これからも仙台で活動を?
東京でも色々と仕事はしていますが、基本的には仙台を拠点にしていたいですね。新幹線を使えば東京にもすぐ出れるので、朝10時に東京で撮影があっても当日の朝に仙台を出発すれば間に合うという地理的なメリットもあります。
ー 仙台で制作するなかで、もっとこうしたサポートがあったらいいなと思うことはありますか。
映像制作に関して言えば、とても具体的ですが仙台にも撮影機材のレンタル屋があったらいいなと思います。レンタル屋は大都市にしかなく、いつも宅配便で送ってもらっているんです。今はそれが主流なのでしょうがないんですけど、近くにあったら明日急に必要になったとしても助かりますよね。あるいは、フリーランスの方で機材をシェアできる環境があってもいいのかもしれない。仙台では予算の大きい仕事は限られてしまうので…。フリーランス同士が交流できる場はたくさん生まれていますが、機材のシェアなどができる場もあったらいいですよね。

ー 今後、撮りたい作品やチャレンジしたい表現があれば教えてください。
しばらく仙台にいるつもりなので、仙台に住んでいる表現者の記録をドキュメンタリー映画にできたらいいなと思っています。公開するかどうかはまだわからないんですが、民話採訪者・小野和子さんの活動を追っていたり、仙台のバンド・yumboの澁谷浩次さんがソロアルバムを録っていてそのレコーディング風景を記録しています。自分が暮らす町にも面白い活動をしている人や撮るべき時間を過ごしている人がいると思うので、遠くへ出かけて行って何かを撮るというよりは、身近にいる人や場所を作品にできたらいいなと思っています。
あとは、映画の上映会をやってみたいですね。コロナ禍でそうしたことも積極的にできなくなりましたが、僕自身やっぱり高校生の頃に仙台でジョン・カサヴェテスの特集上映などに通った経験が大きかったので、配信全盛になった今こそ、そうした上映会をやってみたいなって思います。
ー ぜひ、お願いします…! 上映したい作品はありますか?
いっぱいあります(笑)。全国的に自主上映が評価されている動きもあり、「肌蹴る光線」や「Gucchi’s Free School」など、小さいながらも上映会を企画したり、未公開の映画に自分たちで字幕を点けて上映するチームも出てきている。すごく面白いなって思います。仙台ではまだそういう取り組みが少ないので、やってみたいですね。
ー 今は家でもたくさん観れるけれど、ふとスクリーンの光線を求めてしまったり、みんなで観るという経験はやっぱりいいですよね。
先日、メディアテークで行った『飯舘村に帰る』のバリアフリー上映会で、久しぶりにみんなで映画を観るという経験をしました。みんなで観ると、映像のなかでおばあちゃんがふと発した一言でみんなで笑い合ったりなど、ひとりで観てるときには起きないことが起こるんです。震災の記録で笑い合ったりできるのって、なんかいいなって。
今回、コロナの巣ごもりで友人にプロジェクターを借りて、家にスクリーンを張りホームシアターを豪勢にやっていたんです。最初はテンションが高まり「これで映画館なんていらない…」なんて思っていたけど、やっぱりひとりで観ててもなんかだんだんと虚しくなってくるんですよね。映画っぽい状況がつくれるからこそ、足りないものが明確になって余計に虚しさを感じて。みんなで映画を観るという経験は、わざわざつくらないとないんだと実感しました。本をつくって届けるときのように、映画も自分をつくったものを届け上映するところまで考えてもいいかもしれない。単に観て終わりではなく、みんなで観る場をつくったり、どう届けるかというところまでトータルに考えていきたいです。
ー 最後に、仙台でクリエイターとして働きたいと考えている方に向け、メッセージをお願いします。
仙台は必ずしもスペシャリストではなくても活動していける、いろんな方法や仕事のあり方を選べる余白がある場所だと思います。すでにある方法に合わせるのがしんどかったら、こちらからこうやりませんかというような提案をしたり、そういう話ができる相手を探して一緒に仕事をしてみたり。僕がメディアテークの記録映像の制作に携わるようになったのも、震災後にボランティアに参加して濱口さんや同じく記録や表現活動をする人たちに出会ったことが大きかったので、自分の興味のあるところに顔を出したり、実際に自分でつくってみたりすると、そういうつながりが自然と生まれてくるように思います。

福原悠介(ふくはら・ゆうすけ)
1983年宮城県仙台市生まれ。映像作家。アートプロジェクトや民話語りなど、地域の文化を映像で記録するほか、「対話」をテーマとしたワークショップをおこなう。主な監督作に『家にあるひと』(2019)、『飯舘村に帰る』(2019)など。また、小森はるか監督『空に聞く』(2018)、小森はるか+瀬尾夏美の『二重のまち/交代地のうたを編む』(2019)などに参加。記録集「セントラル劇場でみた一本の映画」企画・編集。
- Web : https://www.petrajp.com/
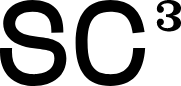
![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)








