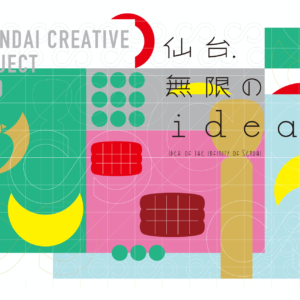【連載】ぼくらは、デザイン論をカウンターで語る。NON DESIGNERS DESIGN RULE 太田伸志|第一回「氏ノ木」小林弘幸

仙台で活躍する経営者たちのほとんどが、⾃分のことをデザイナーとは名乗らない。しかし、デザインとは本来、課題解決のためのプロセスだ。そう捉えれば、彼らの仕事や判断の中にある“無意識のルール”は、驚くほどデザインに満ちている。クリエイティブカンパニーSteve* inc.代表で、コーヒーと⽇本酒を愛する太⽥伸志が、⻑年抱いてきた仮説を確かめるために、彼らが経営するお店を訪ねる連載企画。カウンターの向こうにある、デザイナーこそが本当に学ぶべき「名もなきデザイン論」とは。

1981年宮城県岩沼市生まれ。2015年株式会社はくたい設立。同年に「氏ノ木」本店を開店。現在は仙台市を中心に、「氏ノ木」、「とんかつ牡丹 」のブランドで複数の飲食店を運営している。また、ウェディング事業である「HAKUTAI WEDDING」など、多角的な事業展開も行なっている。 
1977年宮城県丸森町生まれ。東北学院大学経済学部卒。東北と東京を拠点とするクリエイティブカンパニー、Steve* inc.(https://steveinc.jp)代表取締役社長。企業や地域の現場に身を置きながら、プロセスとしてのデザインを実践し続けている。東北芸術工科大学講師。コーヒーソムリエ、唎酒師。
第⼀回「⽒ノ⽊」⼩林博幸のデザインルール
⽬の前を、とにかく⼀⽣懸命やる。
真っ⽩な暖簾の先に。
開店前の居酒屋は、街の裏側みたいだと思う。看板はまだ店内で眠っていて、お客さんの声はない。あるのは精密にリズムを刻む、換気扇と包丁の⾳だけだ。
仙台駅から⻄へ向かって続く、⼈が⾏き交う⼤通りの⼀つ、南町通り。だが、裏側の路地に⼀本⼊ると、時間が少し緩む。さっきまでの賑わいが、遠くに置き去りにされたような静かな通りだ。そこに、真っ⽩な暖簾を掲げた美しい佇まいのお店がある。究極のアジフライで知られる名店、⽒ノ⽊(しのぎ)である。
現在は、気軽なカウンター席が⼈気の⽒ノ⽊2や、座敷も備えたニュー⽒ノ⽊、そして低温調理のレアな豚⾁を使ったとんかつ牡丹など、いずれも⼤⼈気の飲⾷店を系列に持つ。
誰がどう⾒てもイケイケでノリノリの勢いがある仙台の飲⾷店グループ。経営者もイケイケでノリノリだったらどうしよう。仲良く話せるかなぁ。そんなことを考えながら、グループの原点となったこのお店の暖簾をくぐる。
⼀秒後。温かく迎え⼊れてくれた⼩林さんの爽やかな笑顔を⾒て、不安は揚げ物の⾷感のごとく「サクッ」と消し⾶んだ。



追いつけるかではなく、残せるか。
「憧れだったんですよ、仙台は」
⼩林弘幸。⽒ノ⽊グループの社⻑であり、今でも厨房に⽴ち続ける現役の板前だ。いまや⽒ノ⽊は予約が絶えない⼈気店だが、ここに⾄るまでの道のりが平坦でなかったことは想像に難くない。努⼒の原動⼒を探ろうと投げかけた問いに返ってきた⾔葉は、驚くほど軽やかで、そして謙虚だった。
「岩沼市出⾝なんですが、買い物するにしても、⾷事をするにしても、やっぱり仙台だったんです。ずっと憧れていた街ですね。いま、その仙台で、こうして⾷を通して仙台の魅⼒を伝える仕事ができているということ⾃体が、正直まだ信じられない。⼩さい頃の⾃分に教えてあげたいですよ」
仙台は、ときに「東北の都会」として語られる。確かに、僕が学⽣時代の頃に⽐べて、東京で流⾏っているファッションがいち早く店頭に並び、東京で話題のチェーン店で最新のスイーツも楽しめるようにもなった。東京にはあるけれど、仙台にはないものは。何をつくれば東京に追いつけるか。そんな勝負をしているようにも⾒える。だが、⼩林さんはその⽂脈で都会を語らない。
「東京にあるけど仙台にない。とかそういう話じゃないんです。どれだけ“追いつけるか”じゃなくて、どれだけ“残せるか”。油断するとすぐに無くなってしまう⼤切なものが、まだ仙台には残っていると思うんですよね。そこが格好いい」
海が近く、⼭も近い。⾃然との距離も近く、⽣活の形は時代とともに変わってしまったかもしれないが、それでも季節の移ろいははっきりとして、⾷べ物も素材⾃体が美味しい。それらはあまりに当たり前で、だからこそ⾒過ごされがちだ。だが、彼はそこにこそ仙台という街の潜在的な強さがあるという。
⼤⼈になるにつれて、いつの間にか⼿放してしまう仙台への憧れ。それを、今でも胸の奥に残している⼩林少年の姿が、⼀瞬、重なって⾒えた気がした。


⾃分が変わったほうが、無駄がない。
下積み時代からの話を聞くと、最初から和⾷⼀筋だったわけではないという。繁盛店で学べることを優先し、彼が最初に⾶び込んだのはアジア料理の世界だった。現場は想像を超える忙しさだったらしい。けれど、もともと器⽤だった⼩林さんは、どんな味でも受け⽌める⽩ごはんのように、そこで⼀気に⼒を伸ばしていく。
「僕は料理上⼿なんだって思い込んでいました。結構天狗でしたね」
だが、その⾃信は、和⾷の世界に⾜を踏み⼊れた瞬間、あっさりと砕かれる。
「でも、その後和⾷のお店に⾏ったら、ぜんぜんダメでした。それまで積み重ねてきた経験が、まったく評価されなかったんです」
評価されていたお店から⼀転、まったく通⽤しない環境へ。プライドが傷つかなかったはずがない。飲⾷の世界は短期間での⼊れ替わりが激しい。合わなければ次へ、という選択肢もあったはずだ。そう尋ねると、⼩林さんは少し考えてから、こう答えた。
「確かに厳しかったですし、理不尽なこともあったかもしれません。でも、どこに⾏っても⼤変なことはあると思ったんです。理想の場所を探し続けるよりも、⾃分が変わった⽅が無駄がない。どんな環境でも学べることってあるじゃないですか」
その店に、結果的に7年間在籍し、独⽴した。驚いた。⼈気飲⾷店の経営者というと、もともと天才肌で、揺るがない⾃分の世界を持った⼈物像を想像しがちだ。だが、⼩林さんは違う。環境のせいにすることもなく、状況に愚痴をこぼすこともなく、どんな場所でも学びを拾い上げながら、静かに⼒をつけていったタイプだ。
⽩ごはんのように受け⽌めるだけではない。⽕を通したナスのように技術を吸収し、⾼野⾖腐が出汁を抱え込むように基礎を⾝体に染み込ませ、お麩のように、その場の空気ごと取り込んでいく。派⼿さはない。けれど、時間とともに味が深まっていく。ナスの煮浸し定⾷のような成⻑だな、と感⼼した。



何か起きたら、その都度みんなで考える。
あらゆる環境を乗り越え、さまざまな経験を糧にしてきた⼩林さん。現在ではグループ全体で、アルバイトを含め40名を超えるスタッフを抱えるまでになった。組織を率いる⽴場として、ここだけは⼤切にしている「ルール」のようなものはあるのだろうか。そう尋ねると、返ってきた答えは驚くほどシンプルだった。
「その⽇、⽬の前にいるお客様に対して、どれだけ真剣でいられるか。そこの軸だけはぶれないようにしています」
経営理念というには、あまりにも⽬の前のことすぎる。けれど僕は、この⾔葉に強く共感した。インクルーシブ、ダイバーシティ、SDGs。世の中には、⽿障りが良く、明るい未来を約束してくれるような⾔葉があふれている。もちろん⼤切な視点だ。だが、遠くに輝く理想だけを⾒つめていると、⾜元がおろそかになることもある。未来は、⼀⾜⾶びにはやってこない。⼀歩ずつ今を踏みしめながら近づいていくものなのだから。
「僕ら、グランドメニューが無いんです」
⼩林さんは、そう続けた。
「その⽇の仕⼊れで、いいものがあれば、それをどう出すかは各店舗に任せています。急にお客様からメニューにないものを⾔われても、あるものを⼯夫してつくったり。その場のアドリブをお客様もスタッフも⼀緒に楽しめたらいいなって」
デザインの仕事もそうだなと思う。成功を約束されたメソッドなんて存在しない。⼤切なのは相⼿と向き合うこと。どんなことを⽬的とし、何に悩み、何を解決したいのか。その問いに対してどう応えるかを考えるところから、仕事は始まる。⼤変な作業ではあるが、そこに⾃分らしい仕事につながるヒントがあるのだと思う。だだ、マニュアルのない現場は、負担も⼤きいはずだ。スタッフの反応はどうなのだろうか。
「そういうのが、うちらしいねと⾔ってくれています。何か起きたら、その都度みんなで考える。効率的じゃないかもしれませんが、僕もうちらしいと思っています」
確かに、世の中はあまりにも効率を求めすぎているのかもしれない。だが、効率とは本来、余⽩をつくるための⼿段のはずだ。すべてを想定内に収めてしまえば、想像を超える出来事に出会う機会は失われてしまう。⽬の前に真剣でいること。それは、視野を狭めることではなく、むしろ遠くまで旅をするために必須のルールなのかもしれない。⼩林さんは、⽬の前を⼀つずつ⼤切にすることで、結果的に遠くまで歩いてこれたのだ。



向き合うべきは、⼈間らしさ。
そういえば今や、仙台のさまざまな和⾷店で、周りがサクサク、中⼼がレアの状態で提供されるアジフライを⽬にするようになった。もはや⼀つのカルチャーになりつつある、仙台のアジフライブーム。その⽕付け役ともいえるのが、⽒ノ⽊だ。始まりのきっかけは、どんなものだったのだろうか。
「あれ、もともと失敗したアジフライだったんです」
緻密な計算によって⽣まれた最⾼傑作、そんなイメージを勝⼿に抱いていた、⽒ノ⽊の看板メニュー「究極のアジフライ」。その名に反して、返ってきた答えは意外なものだった。
「油が⾼温になってしまっていて、中まで⽕が通らなかったんです。でも、⾷べてみたらめちゃくちゃ美味しくて。知り合いのお客様に出してみたら絶賛されて。それで次の⽇も出すようになったんです」
始まりは、失敗。けれど、そこにはお客様との信頼関係に裏打ちされた⾃信があった。デザインとは、やはりプロセスなのだと確信した。流⾏りのメニューやカルチャーは、PhotoshopやIllustratorから⽣まれるのではない。失敗、迷い、信頼。すべては、そんな⼈間らしさから⽣まれるのだ。
「ちなみに、話題のきっかけをつくれたことは嬉しいのですが、レアアジフライというジャンルを本当に早くやっていたのは、⼤町のニコルさんだと思います。⼤好きで、尊敬しているお店です」
流⾏の中⼼にいるはずの⼩林さんは、そう⾔って、少し照れたように笑った。同じく仙台の名店である「ニコル」の名を、迷いなく挙げたその様⼦を⾒て、僕は気づいた。⼩林さんの凄さは、0から1を⽣み出すことだけではない。誰かが始めた1だとしても、それを丁寧に噛み締め、2や3へと育てる⼒だ。それがいつのまにか80や90となり、気づけば、ここまで来ていたのだと思う。
「もちろん、⾻で器をつくったり、⽒ノ⽊だけの味は⽬指し続けています。あ、⾷べていきます?」
そう⾔って厨房に⽴つ⼩林さんは、誰よりもエプロンが似合っていた。カリカリに揚げきった正解で固めてしまうのではなく、あえて⽕の通っていない部分を少し残す。⽒ノ⽊のアジフライを⾷べながら、⼈⽣も、たぶんそれぐらいがちょうどいいのだと思った。

写真:SENCE OF WONDER
インタビュー・⽂:太⽥伸志(Steve* inc.)
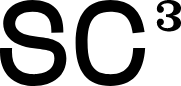
![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)